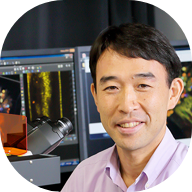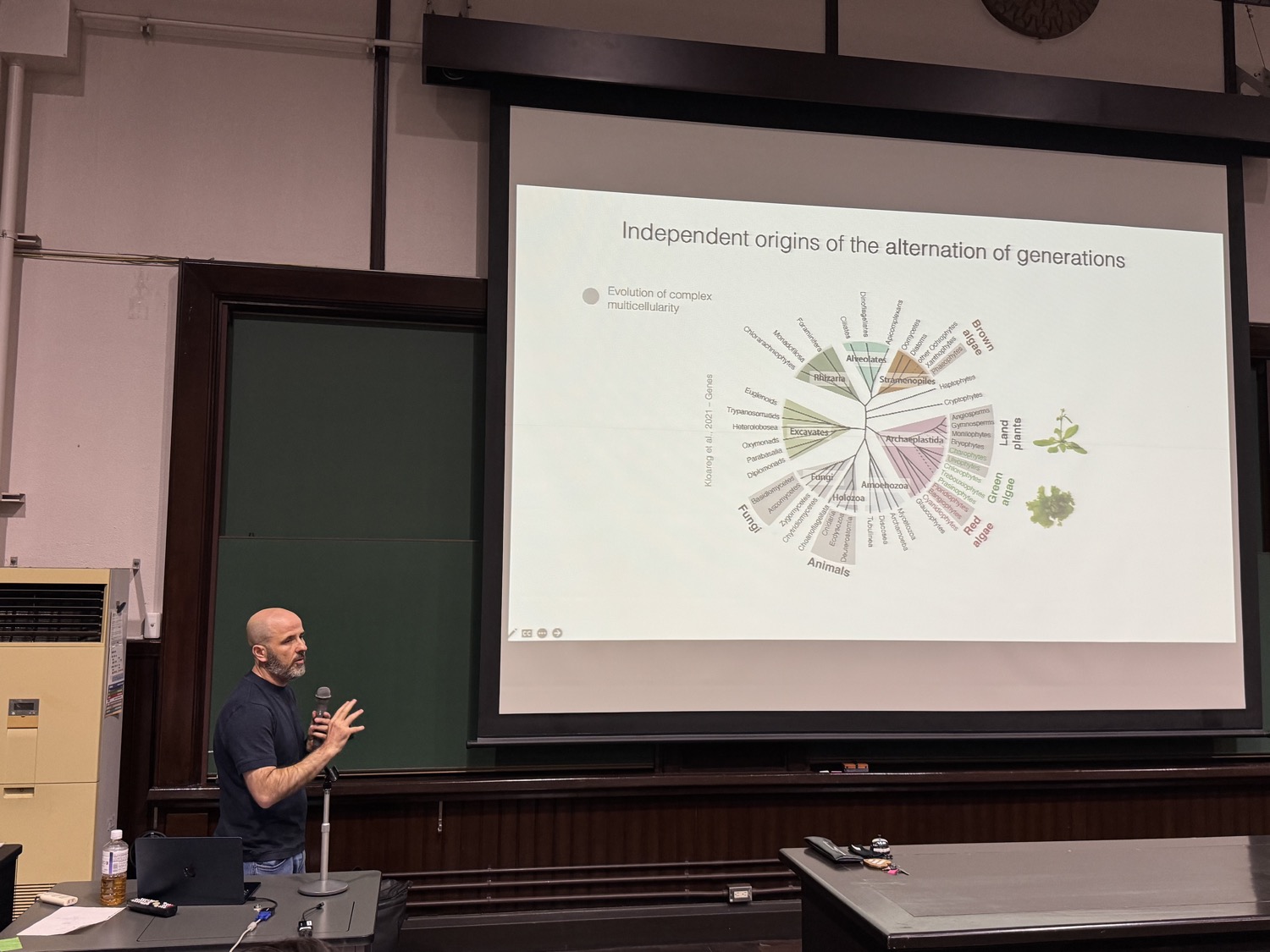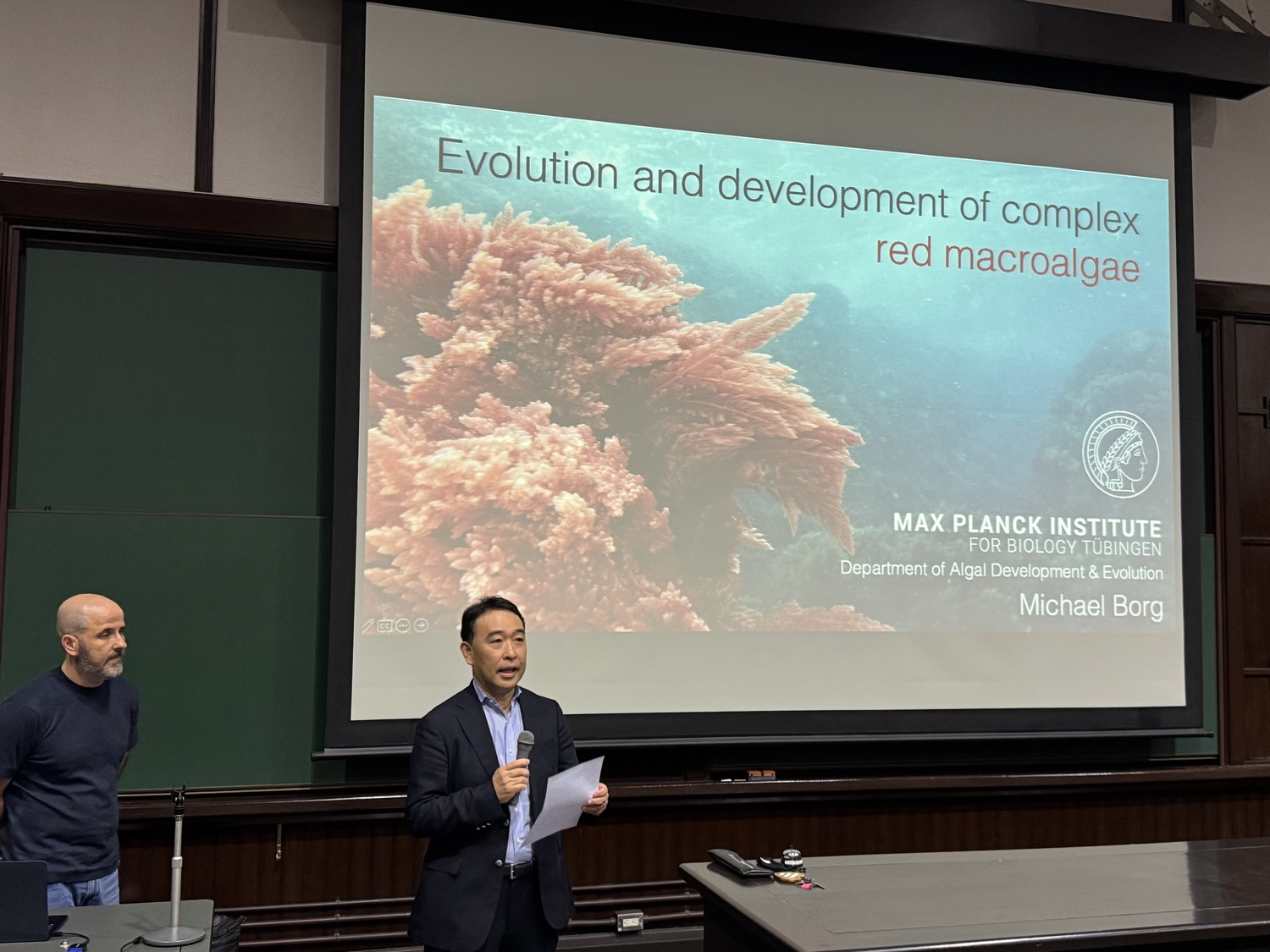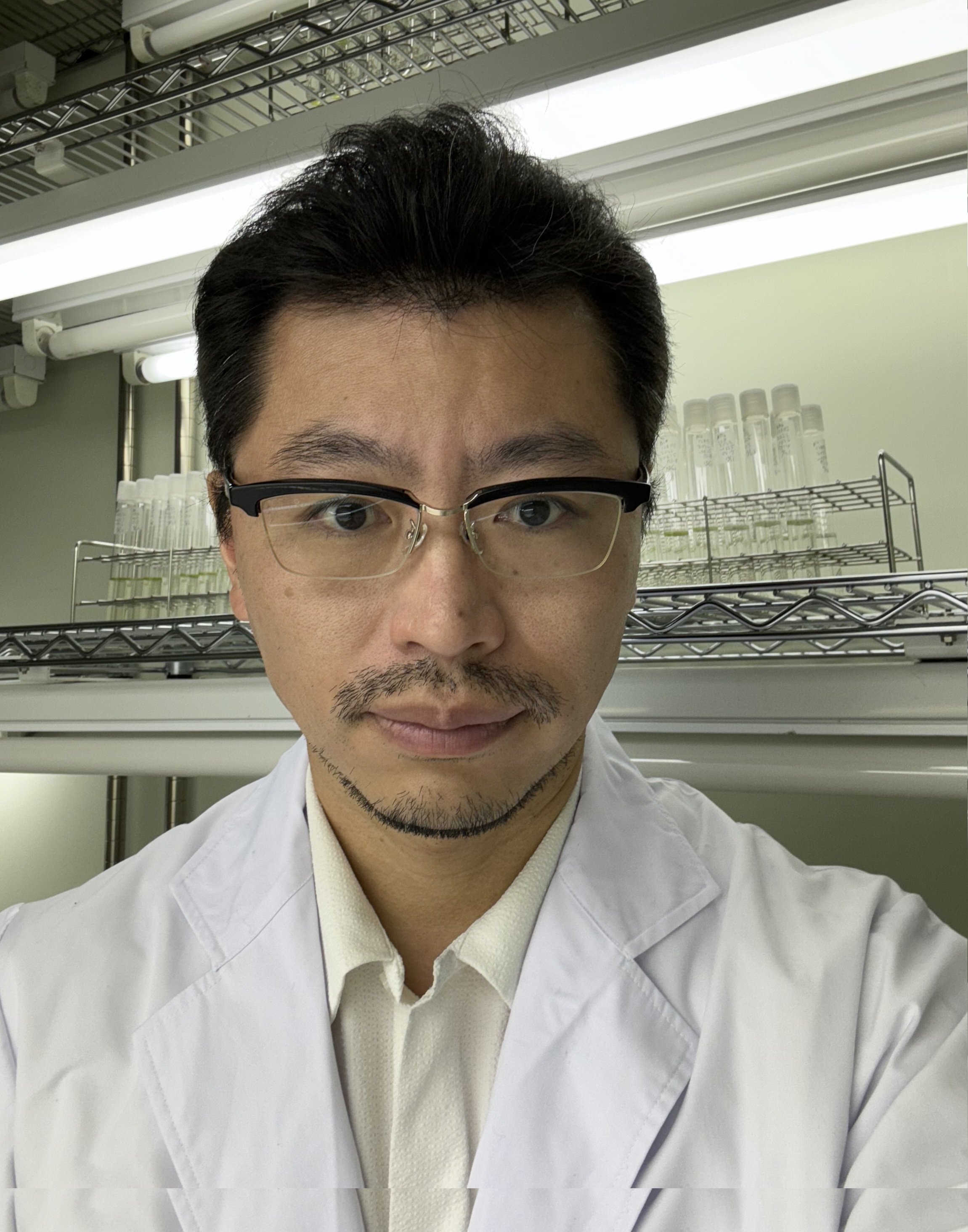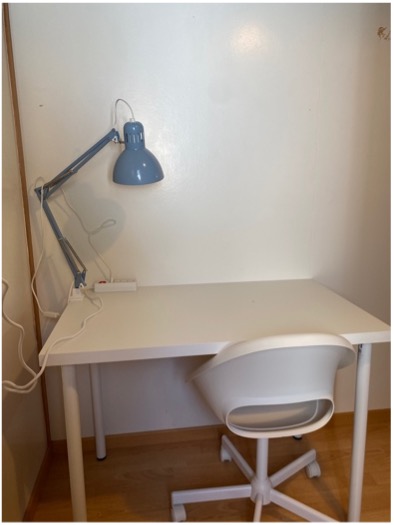渡航報告:EMBO Workshop in Vienna, Austria
11月末、筆者は遥かオーストリアの地で開かれる国際学会に参加するべく、一人欧州へと飛んだ。ほんの数日の滞在とはいえ、異国の魔力はいつだって旅人の心をざわつかせる。せっかくの機会なので、ここに拙いながらもその紀行を残しておこうと思う。 暖まったところで、自然史博物館へ足を向けた。重厚な歴史的建造物の内に地球の歴史と生命の軌跡がこれでもかと言わんばかりに詰め込まれ、巨大な骨格標本や鉱石の山が見る者を容赦なく圧倒してくる。あまりの情報量に半ば処理落ちしながらふらふらと歩いていると、気づけばまたクリスマスマーケットへと辿り着いていた。ライトアップされた市庁舎が天を衝くように輝き、広場全体が幻想的な光に包まれている。もはや映画のワンシーンである。むろん、ここでもグリューワインを補給する。どうやらウィーンの冬は、この霊薬によってのみ攻略が可能らしい。 さて、肝心の学会である。今回参加した EMBO Workshop は植物の進化をテーマとしており、ここでは藻類、コケ、シダといった“花のない植物”が華型であった。専らコケやシダを扱う筆者としては、まさに水を得た魚のような心持ちである。最新技術を駆使した研究成果に唸らされ、久しく触れてこなかった話題に再び向き合えるのも、得難いよろこびであった。
学会前日に到着した筆者は、チェックインまでの暇をつぶしに街へと繰り出した。冬のウィーンは、想像していたよりもずっと手ごわい。最高気温 2°C というのは、常識的に考えて外出を控えるべき寒さである。外へ一歩踏み出すたび、「ようこそ冬のヨーロッパへ」とばかりに冷気が頬を刺し、心を折りにかかってくる。それでも街はクリスマスの熱気に包まれており、寒さと賑わいが混じる独特の活気を放っていた。
まずはクリスマスマーケットなるものを一目見ようと、筆者はシェーンブルン宮殿を訪れた。そこでは宮殿とお揃いのイエローで着飾った屋台たちが「どうだ、可愛かろう」と整列していた。歴史ある王宮を背景に手工芸品がずらりと並ぶ光景は、なにやら絵本の世界に迷い込んだようですらある。そこで飲んだグリューワインは、魔法の霊薬さながらに冷え切った身体を瞬時に蘇生させてくれた。

思いがけず 、Gregor Mendel Institute を見学する幸運にも恵まれた。名高い研究所の内部には最新鋭の機材がこれでもかと並び、世界の知がポンポン生まれるさまが目に浮かんだ。圧巻の設備に感嘆しつつも、研究を支えているのはやはり人の発想と工夫であるという事実が、むしろ強く心に残った。若手からシニアまで、こと研究となると目を輝かせる。結局のところ、研究の価値を決めるのは機械ではなく人なのだと、深く感じ入った。
ウィーンでの数日は非日常感に溢れ、じつに刺激的であった。寒空の下で賑わう街も、研究を語る人々の顔つきも、しばらく胸に残り続けるだろう。ひるがえって自身の研究はどうであろうか。まだまだ道半ば、どこから手をつけよう。やる気も新たに帰途についた。